こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「消費税申告は簡易課税制度を使えば得って聞いて申請したけど、実際得なのか分からない…」
「数年前に比べて売上が結構落ちたけど、まだ簡易課税制度を続けたほうがいいのかな…」
そんな疑問を持つクリエイターさん、少なくないと思います!
そこでこの記事では、簡易課税制度をやめるべきタイミングについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
そもそも「簡易課税制度」ってなに?
周りにおすすめされるがままに簡易課税制度選択の届出をしたはいいものの、
正直どんな制度かきちんと理解できてないって人も少なくありません。
そこで、あらためてざっくり説明すると、
消費税の納税額を「売上に乗っかっている消費税額」をもとにして簡単に計算できる制度です。
- 原則の計算方法:売上に乗っかっている消費税額 − 経費に乗っかっている消費税額
- 簡易課税の計算方法:売上の消費税 × みなし仕入率(クリエイターさんは基本50%)
ポイントは、経費に乗っかっている消費税額がいくらであっても、
簡易課税制度を適用する場合は、
売上に乗っかっている消費税額に一定割合をかけた金額だけ納税すればいいということ。
つまり、ある年から売上がいきなり伸びても、経費が増加しにくいクリエイターさんの場合なら、
簡易課税制度を使ったほうが税額が安くなるだけでなく、申告も楽に済ませられるという利点があります。
注意点はコチラ👇
- 2年間は継続適用しなきゃいけない
- やめる場合は、前年の終わりまでに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要あり
- 原則計算のほうが税金が安くても、課税制度選択期間中は原則計算不可
- 2年前の課税売上高が5,000万円を超えてる場合は、届出をしていても原則計算が必要
ちょっとわかりづらいかもですが、
やめたくてもいきなりやめることはできないものと考えておけばひとまずOK!
◆おすすめ記事


検討タイミング① 経費・設備投資の金額が大きく増えそうなとき
簡易課税は、経費に乗っかっている消費税額を「みなし」で計算する制度なので、
経費の金額が増えてきたときや、高額な設備投資をするときには、
「みなし」で計算するよりも、その年実際に支払っている消費税額のほうが多くなる可能性があります。
たとえば、
- 高額なPCやカメラ、編集用ソフトをまとめて購入する予定
- 事業用に使っている車を買い替える予定がある
- 住居とは別に事業用オフィスを借りて、毎月の家賃に消費税が含まれている
こういう場合は、一時的にでも簡易課税をやめたほうが納税額を安くできるかもしれません。
◆おすすめ記事

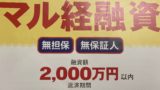
検討タイミング② 売上が大きく減少してきたとき
簡易課税は、「売上に乗っかっている消費税額」をもとに消費税を計算するので、
売上が下がれば消費税額もそれに応じて下がっていきます。
ただ、売上額が減少しても毎月の経費金額が変わりにくいクリエイターさんの場合は、
売上が減少することで、結果的に経費割合が大きく増加する可能性があり、
「売上に乗っかっている消費税額× 50%」で計算すると損になることも珍しくありません。
そのため、
- 簡易課税制度を選択した当初に比べて印税収入が落ちてきた
- 毎年継続していた大型案件が打ち切りになった
- 案件数が毎年減少傾向にある
こういった場合には、簡易課税制度をやめるべきか検討してみるのがおすすめです。
◆おすすめ記事


検討タイミング③ 主要な作業を外注先に任せる案件が増加したとき
これは①と似ている話なんですが、
主要な作業を外注先に任せる案件の場合、売上の50%以上を外注先に支払うケースってありますよね。
(作業そのものは外注先に依頼して、自分はディレクションや最終チェックを行うなど)
規模を拡大していく過程でそういった案件が増えてくると、
外注費が増加することで売上に対する経費割合が増加し、
これもまた原則計算のほうが消費税額が安くなる原因につながります。
これに限らず、多種多様な材料の仕入れ、高額な素材購入、高額なスタジオ利用など、
売上に応じて直接的に原価がかかる案件の割合が増えてきた場合には、
簡易課税を続けるべきから、検討してみる価値アリです。
◆おすすめ記事


結局は経費割合がカギ
ここまで見てきたとおり、簡易課税制度をやめるべきかどうかの判断においては、
「売上に対する経費割合がどれくらいあるか」がカギになります。
そのため、ざっくりとした目安ではありますが、
簡易課税制度を続けるべきかどうか一つの目安として、こんな計算をしてみてください👇
- 売上高 - 調整経費(※)で算出した利益が、売上の50%以上か
※調整経費:経費総額 - 専従者給与・従業員給与 - 減価償却費 - 租税公課 - 住居の地代家賃
(あえて調整経費を使う理由は、「消費税が乗っかっていない経費」を除外するため。)
この結果が50%以上であれば、
簡易課税制度を使ったほうが消費税額が安くなる可能性が高いです。
もちろん、厳密には海外取引の有無、設備投資の金額も考慮する必要がありますし、
簡易課税ならインボイス番号が記載された領収証を紛失してもOKというメリットがあるので、
「ちゃんと考えておきたい」という場合には、税理士に相談してみることをおすすめします!
◆おすすめ記事


Q&A:簡易課税に関するあるあるなお悩み
Q. 「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」って自分でもつくれる?
A. はい!国税庁のHPよりPDFファイルをDLして、
「消費税簡易課税制度選択不適用届出手続 書き方」とネット検索すれば、自分ですぐ作れます!
e-Taxで作成、提出する方法もあります。
Q. 事務コストの観点で簡易課税制度を使い続けるのはアリ?
A. はい!実際のわたしのお客様のなかにもそういったご要望の方がいます。
原則計算と簡易課税で計算される消費税額に大きな差がなければ、全然アリな選択です。
まとめ │ 簡易課税をやめるべきかは「経費割合」で判断
- 経費が多くなることや、多額の設備投資の予定があるときは原則計算のほうが有利
- 売上減少により、結果的に経費割合が増加する場合も原則計算のほうが有利
- 売上に対する経費割合を計算してみて、今の状態をなんとなくでも知るのが大事


